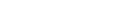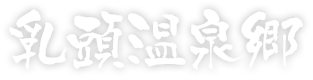乳頭温泉郷 歴史年表
現存する資料などを基にまとめた乳頭温泉郷の歴史年表をご紹介します。
| 年号 | 出来事 | 詳細 | |
|---|---|---|---|
| 先史時代 | 三角錐の岩に刻まれた古代象形文字(ヒエログリフ)と思われる文様が1995年歴史研究家鈴木旭氏によって先達川沿い(妙乃湯)で発見される。 | 目と涙を象ったとされ、祈りや水のある場所を意味する。豊かな森の恵みを求め、狩猟や採取のために人間が移り住んでいたのだろう。温泉湯治をしていたのかもしれない。 | |
| 江戸時代 | 1615年(元和元年) | 鶴の湯温泉開湯 | 開湯当初は「田沢の湯」と呼ばれる。 |
| 1638年(寛永15年) | 佐竹義隆鶴の湯へ入湯 | 二代目秋田藩主佐竹義隆が鶴の湯に湯治で訪れたと云われている。 | |
| 1661年(寛文1年) | 岩城玄蕃鶴の湯へ入湯 | 亀田藩岩城玄蕃が鶴の湯に湯治で訪れたと云われている。 | |
| 1674年(延宝2年) | 黒湯温泉開湯 | 佐竹北家の前の角館の殿様、芦名氏やその家臣らが湯治したという記録が残っている。明治の中頃までは「亀の湯」とも呼ばれていた。 | |
| 1681年(天和元年) | 鶴の湯温泉開業 | 羽川六右衛門氏が湯守として経営を始める。 | |
| 1708年(宝永5年) | 田沢の湯から鶴の湯へ | 鶴が傷を癒しているところを勘助というマタギが見たところから「鶴の湯」と呼ばれるようになる。 | |
| 1846年(弘化3年) | 蟹場温泉開湯 | 下桧木内村の医師太田泰文氏と春山の医師鬼川良策氏が発見したと云われている。 | |
| 1850年(嘉永3年) | 蟹場温泉開業 | 鬼川良策氏が蟹場温泉に自炊宿を開業した。名前の由来は近くの沢に沢蟹が多くいることから。 | |
| 明治 | 1902年(明治35年) | 孫六温泉開湯 | 農林技師桜井啓氏によって発見されたと云われている。 |
| 1906年(明治39年) | 孫六温泉開業 | 創業者の田口久吉氏は体が弱く、黒湯温泉に湯治中、散歩していたら温泉が湧き出ているのを発見し、笹小屋を建て湯治を行なった。明治39年に客室を建設し、一般客を受け入れ始めた。久吉氏は孫六温泉までの山道を整備した記録が現在も石碑として残っている。 | |
| 大正 | 1923年(大正12年) | 国鉄生保内線開通 | 大曲-生保内(現・田沢湖駅)に国鉄が開通。 乳頭温泉郷へは生保内駅(現・田沢湖駅)から徒歩で約5里20km約6時間の道のり。当時は先達川沿いに山道があり生保内―鶴の湯―蟹場―黒湯・孫六がメインルートだった。 |
| 昭和 | 1929年(昭和4年) | 黒湯温泉 池田家へ継承 |
黒湯温泉の管理者田代氏から池田家へ継承された。 |
| 1952年(昭和27年) | 妙乃湯温泉開湯 | 創業者後藤定二氏は終戦直前に樺太から帰還し、稲作、豆腐製造、杜氏、歩荷などを生業にしていたが黒湯温泉への荷揚げ作業中、温泉を発見した。 | |
| 1953年(昭和28年) | 鶴の湯温泉「旅館部」設置 | この頃から乳頭温泉郷は湯治客を泊める他に客室を設けるようになった。 | |
| 1955年(昭和30年) | 妙乃湯温泉開業 | 後藤定二氏は56歳で先達川沿いに温泉旅館を開業した。 | |
| 1956年(昭和31年) | 十和田八幡平国立公園制定 | 乳頭山麓宿舎事業として鶴の湯、黒湯、蟹場温泉、孫六温泉、妙乃湯が認可される。 | |
| 1959年(昭和34年) | 道路整備が進む、乳頭温泉郷 | 西山生保内線 県道に認定。 営林署の事業用林道「鶴の湯線」開通。車の乗り入れが可能になる。 |
|
| 〃 | 入湯税田沢湖町条例制定 | ||
| 1960年(昭和35年) | 国民宿舎駒草荘開業 | 田沢湖高原エリアに駒草荘が開業。道路整備とともに観光開発が進んだ。 | |
| 1961年(昭和36年) | 乳頭山および秋田駒ケ岳が第16回国民体育大会秋季大会登山部門の会場に指定 | これをきっかけに乳頭温泉郷は八幡平方面への登山縦走の基地として注目を浴び始める。この頃から各温泉宿は旅館部といった従来の湯治型ではない観光客を対象とした宿泊施設の充実を図っていった。この年にレジャーブームが始まる。 | |
| 1962年(昭和37年) | 大釜温泉開業 | 名前の由来は源泉の釜が大きかったことから。それまで乳頭温泉郷では源泉が出る場所に宿舎を設けていたが、大釜温泉は引湯管で温泉を引き込み県道沿いに宿を開業させた初めてのケース。 | |
| 1963年(昭和38年) | 羽後交通「鶴の湯線」バス運行開始 | ||
| 1964年(昭和39年) | 国民休暇村誘致 | ||
| 〃 | 国道46号線(秋田-盛岡)が全通 | 物流・観光の基幹として開通した。 | |
| 〃 | 黒湯温泉離れ別荘新築 | 春スキーで訪れた高松宮殿下の来訪に合わせて黒湯温泉の離れ別荘が建築された。 | |
| 〃 | 東京オリンピック開催 | 日本およびアジア地区で初めてオリンピックが開催された。 | |
| 1965年(昭和40年) | 田沢湖高原国民休暇村(現・休暇村乳頭温泉郷)開業 | 現・一般財団法人休暇村協会により全国15か所目の施設として開業。同時に国民休暇村乳頭スキー場も開設。田沢湖町(現・仙北市)はカラ吹き湿原を掘削し新たな温泉を開発した。田沢湖高原へ供給すると共に、休暇村にも供給を開始した。開業と同時にバス路線(羽後交通乳頭線)も休暇村まで開通した。 | |
| 1966年(昭和41年) | 国鉄生保内線・橋場線が全通 | 全通により田沢湖線と改称された。秋田県仙北郡と岩手県盛岡市が鉄道で結ばれる。 | |
| 1967年(昭和42年) | 乳頭温泉郷および田沢湖高原温泉郷が国民保養温泉地に指定 | ||
| 1969年(昭和44年) | 大釜温泉 佐藤和志氏が経営開始 |
昭和41年頃に和志氏の父(五郎氏)が休暇村乳頭温泉郷のロッジの建設を請け負う。その頃から五郎氏が大釜温泉の経営をすることになるが、経営難だったという。建物もかなり傷んでいたため修理も重ねた。昭和44年の正月に家族会議の上、和志氏が東京の勤めていた会社を退職し、経営を始めた。 | |
| 1970年(昭和45年) | 駒ケ岳女岳噴火 | 死傷者。家屋への被害なし。噴火を見物する観光客が急増し生保内町内は大渋滞した記録が残っている。また噴火の夜景が綺麗だったことで宿泊需要が増加し麓には民宿が多数開業した。 | |
| 1973年(昭和48年) | 蟹場温泉本館新築 | 同時に岩風呂新築した。 | |
| 〃 | 高度経済成長 | 全国で交通網が整備されバス旅行が普及しレジャーの形が大きく変化していった。農業も機械化が進み、サラリーマン兼業農家が増加、農閑期に数週間湯治する時間は無くなり湯治という福利厚生もレジャーも終焉を迎えた。 | |
| 1976年(昭和51年) | 国道46号線仙岩トンネル開通 | 田沢湖-盛岡間の通年通行が実現。旧道は九十九折りの道路で難所も多かった。 | |
| 1977年(昭和52年) | 大釜温泉焼失事件 | この年の年末、東京の大学生が無理心中を図り、宿に放火。大釜温泉は全焼する。幸い死傷者はでなかった。大釜温泉の再建は当時の経営者(佐藤和志氏)が出身地秋田県由利本荘市の小学校廃校校舎を移築して行われた。 | |
| 1978年(昭和53年) | 羽後交通「鶴の湯線」バス廃止 | ||
| 1979年(昭和54年) | 乳頭温泉組合発足 | 湯めぐりスタンプ帖がスタート。当時は1冊400円で販売されていた。 | |
| 〃 | 休暇村乳頭温泉郷・新館建設 | ||
| 1981年(昭和56年) | 鶴の湯温泉経営者交代 | 羽川健治郎氏から佐藤和志氏に鶴の湯温泉の経営が委譲される。 | |
| 1982年(昭和57年) | 田沢湖線電化 | 特急たざわが盛岡駅で東北新幹線へ接続。高速交通網が接続したことで首都圏からの所要時間が大幅に減少する。 | |
| 1984年(昭和59年) | 大釜温泉経営者交代 | 大釜温泉の経営者が伊藤十三男氏へ交代する。 | |
| 1985年(昭和60年) | 鶴の湯温泉・新本陣新築 | 名物の混浴露天風呂が出現!掘ったら温泉が湧き出る。 | |
| 1988年(昭和63年) | 大規模リゾート法制定 | バブル経済の中、各地で開発が進む。田沢湖エリアでも秋田新幹線開業にあわせスキー場・ゴルフ場・マリーナ・ホテルなどの複合リゾート開発計画が上がる。(自然保護団体の反対により計画は規模縮小し湖畔のホテルのみ実施) | |
| 〃 | 鶴の湯温泉・東本陣新築 | ||
| 平成 | 1991年(平成3年) | 妙乃湯の後継者として乳頭温泉郷初の女性経営者が誕生 | 妙乃湯の後継者として乳頭温泉郷初の女性経営者が誕生。宿を大幅にリニューアルするなど、女性目線の旅館へ変貌を遂げる。 |
| 〃 | 蟹場温泉・正面左側の自炊棟を現在の新館に建替 | 同時に露天風呂・浴場改装。 | |
| 1992年(平成4年) | 鶴の湯温泉の露天風呂がブルーガイド(実業之日本社)「温泉100選・露天風呂の部」1位に選定 | 10年連続全国第1位に輝いた。 | |
| 〃 | 黒湯温泉・旅館部改装 | ||
| 1994年(平成6年) | 鶴の湯温泉通年営業開始・山の宿開業 | ||
| 〃 | 妙乃湯・椿館新築 | ||
| 1996年(平成8年) | 秋田新幹線工事の為、田沢湖線全面運休 | ||
| 〃 | 黒湯温泉・全面リニューアル工事 | ||
| 1997年(平成9年) | 秋田新幹線開業 | 東京駅-田沢湖駅直通で所要時間3時間。新幹線高速交通網に接続することで乳頭温泉郷へ東京駅から4時間でアクセスが可能になった。 | |
| 〃 | 鶴の湯、妙乃湯では自社のウェブサイト(ホームぺージ)が開設 | この時期Windows95の発売と共にダイアルアップ接続の地域インターネットプロバイダーが設立され、乳頭温泉郷でもインターネットアクセスが可能になる。 | |
| 〃 | 孫六温泉・女性露天風呂を設営 | ||
| 1998年(平成10年) | 日本旅のペンクラブ賞を乳頭温泉郷が受賞 | 受賞を記念した石碑が鶴の湯旧道口バス停付近にある。授賞理由は乳頭温泉組合が地域一体となって温泉文化を守り、観光振興に努めてきたから。これを機に湯めぐり帖のシステムを大幅にリニューアルし現在につながる組合運営の基礎となった。日本旅のペンクラブ(旅ペン)との関係はその後も続き、雑誌やTVへの露出は大幅に増えていった。 | |
| 2000年(平成12年) | 日本観光協会「優秀観光地づくり賞」受賞 | ||
| 〃 | 妙乃湯・桜館新築 | ||
| 2001年(平成13年) | 大釜温泉・浴場改築 | 乳頭温泉郷一大きい露天風呂の浴槽を二つの浴槽に分けた。 | |
| 〃 | 休暇村乳頭温泉郷・大規模リニューアルオープン | ||
| 2002年(平成14年) | 日本経済新聞温泉大賞「あこがれ賞」及び「岩切章太郎賞」(鶴の湯)受賞 | ||
| 〃 | 黒湯温泉・離れ別荘を改築 | ||
| 2003年(平成15年) | 旅行読売出版社「にっぽん温泉遺産100」上位10選受賞 | ||
| 〃 | 大釜温泉・足湯新設 | 乳頭温泉郷初の足湯が設けられる。 | |
| 〃 | 乳頭スキー場休業 | ||
| 2004年(平成16年) | 妙乃湯浴場の改装 | ||
| 2005年(平成17年) | 仙北市の誕生 | 旧田沢湖町、旧角館町、旧西木村の2町1村が合併し発足した。 | |
| 2006年(平成18年) | 観光立国推進基本法成立 | ||
| 〃 | 鶴の湯雪崩事故発生 | 県内は記録的な大雪による事故が続いた。事故後、鶴の湯と孫六の背後にある傾斜地には雪崩止めが設置され、事故防止策が講じられた。乳頭温泉組合でも自然災害に対して地域全体で備え、安全を確保するための対策が進められた。 | |
| 2008年(平成20年) | 観光庁設立 | 日本人の海外旅行に比べて外国人の日本旅行が少ない現状、人口減少を迎える中での経済対策として訪日外国人旅行者増加を目的として観光庁が設立された。インバウンドという用語もこの頃生まれた。 | |
| 〃 | 仙北市観光振興計画が策定される | 遠方の欧米豪からではなく、比較的近い東アジア、東南アジアからの旅行者が増加。2002年サッカーワールドカップ、2005年愛知万博を機に韓国や台湾からの短期観光ビザが発行され、更に中国本土からの団体旅行観光ビザが発給されると大幅に外国人旅行者は増加した。 | |
| 2009年(平成21年) | 湯めぐり号運行開始 | 湯めぐり号は乳頭温泉郷7つの宿を循環しているシャトルバス。湯めぐり帖・湯めぐりマップを購入すると乗車可能。 | |
| 2011年(平成23年) | 東日本大震災 | 岩手・宮城沖を震源とするM9の大地震が発生、乳頭温泉郷付近では震度4、地震による直接被害は無かったが、その後の福島第一原発事故の風評被害や東北・秋田新幹線が不通になった事により来訪者が激減することになる。震災から半年後、乳頭温泉組合では近畿・中部・九州の秋田県人会を訪問し、秋田への里帰り旅行プロモーションを展開、東北や秋田の現状を直接伝えた。東北観光推進機構との連携も始まった。 | |
| 2013年(平成25年) | 乳頭温泉郷ウェブサイト「Ryokan story」「Onsen story」を制作 | 温泉カメラマン杉本氏、日系アメリカ人ライターSami Kawahara氏、温泉ビューティー研究家石井氏らを招聘しグローカルプロモーションが制作。翻訳ではない英語記事を掲載しインバウンド誘致を目指した。この頃から湯めぐり号の大型化(ワゴン車からマイクロバスへ)を実施、乳頭温泉郷アカウントSNSでの情報発信やブナの森を活用した海外のアートイベント、フィールドカフェ事業、eバイクツアーなど、温泉だけではない乳頭温郷の魅力発信をおこなうようになった。 | |
| 令和 | 2019年(令和元年) | 湯めぐり号運行10周年記念セレモニー | 10月10日休暇村乳頭温泉郷の第二駐車場にて記念セレモニーが開催された。 |
| 〃 | じゃらん全国温泉地ランキングの「あこがれの温泉地」で一位を初獲得 | ||
| 2020年(令和2年) | 新型コロナパンデミック | 4月全国に緊急事態宣言が発令されたことを受け、乳頭温泉組合では乳頭温泉郷施設の一斉休業を決定し、従業員への休業補償制度の説明会を実施した。緊急事態宣言解除後には準備の整った施設から順次再開し6月には全ての施設が営業を再開した。8月大曲花火競技会が中止されたのを受け疫病退散祈願花火大会を開催。 | |
| 2021年(令和3年) | 観光庁「既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業」が乳頭温泉組合として採択 | 第一回観光庁地域一体となった観光地再生事業が採択され、コロナ禍による受入態勢の強化・旅行者のニーズに合った施設改修が行われた。10月からはコロナ過でのイベント開催を模索、熱気球体験や自然の中で過ごすAutumnフェスを開催した。 | |
| 2022年(令和4年) | 「御湯印めぐり」開始 | 乳頭温泉郷の湯めぐりのアクティビティコンテンツとして新たに「御湯印めぐり」が開始された。 | |
| 2023年(令和5年) | 孫六温泉経営者引退による休業 | 後継者の不在や従業員の高齢化により事業継続が困難となった孫六温泉。乳頭温泉組合の他6施設は孫六温泉存続の可能性を探り、財団法人休暇村協会以外の5法人で孫六温泉の株式買い取りと増資を行い孫六温泉は実質的に乳頭温泉組合での共同経営体制となる。 | |
| 〃 | 観光庁「地域一体となった観光地再生事業・高付加価値化事業」を仙北市田沢湖地区で採択 | この事業には孫六温泉・鶴の湯温泉・黒湯温泉・蟹場温泉・妙乃湯の5施設が参画している。 | |
| 〃 | 乳頭温泉郷協同組合設立 | 従来の温泉組合という任意団体から県知事が設立認可する法人になった。 |
乳頭温泉郷は湯治客、登山客、スキーヤー、秘湯ブーム、インバウンド訪日外国人客、コロナ過での自然回帰・・・
時代の流れと共に温泉旅館の役割やレジャー形態が変化するなかで、残すべきもの、変わるべきものを判断し、乳頭温泉郷が旅人に愛され続け、先人の功績を未来に残すため、日々努力を続けていきます。